1.�܂悤���@�Ƃ��̃n�u���V�A
�����ĉ������A�����b�g�A�f�����b�g
�@
�@ |
| �u�܂悤���@�v���u���V�̎g�������z |
 �����͎��Ԃ��J���Ă��Ȃ��̂Ŗѐ悪�אږʂɓ��炸�A2��^�A�тȂ̂Ŗ����Ă��ĉ���������Ȃ������ł����B �����͎��Ԃ��J���Ă��Ȃ��̂Ŗѐ悪�אږʂɓ��炸�A2��^�A�тȂ̂Ŗ����Ă��ĉ���������Ȃ������ł����B
���Ԃ��J���Ă�����͐H���c�Ԃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������ɂ���אږʂ͎��u���V�����ł̓v���[�N�����Ƃ��Ȃ��̂Ńt���X�ł̂�����ꂪ�K�v�ł��B
�y�u�c�z |
| |
 �܂悤���@�u���b�V���O�Ƃ́A�ѐ�����ԕ��ɏo�����ꂵ�A�����}�b�T�[�W�����A���u���V�P�{�Ō����悭�ł���Ƃ̎��B �܂悤���@�u���b�V���O�Ƃ́A�ѐ�����ԕ��ɏo�����ꂵ�A�����}�b�T�[�W�����A���u���V�P�{�Ō����悭�ł���Ƃ̎��B
�����b�g�@���Ԃ����Ȃ�Ă���l�ɂ́A�ѐ悪����₷���Ǝv���܂��B
�ʐ^�ł̃u���b�V���O�@�������ĂȂ��̂ŁA���挩���܂����B
http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=OCxaCcdWgbs#t=75s
�f�����b�g�@���u���V���d���B���Ȃ�͂����Ȃ��Ǝ��Ԃɓ���Ȃ��Ǝv���܂��B���������A�ނ������������B
�т��Ȃɂ���d���̂ŁA���̕\�ʂ̓v���[�N���Ƃ�邪�A���z���ɂ͏������S���������Ă��銴��������B�u���V�ł̎��Ԑ��|�Ȃ�A��͂莕�ԃu���V�̕����m�����Ǝv���܂��B
�y�|���z |
| |
 �ꌩ����ƍd���Ė����ɂ��������ł������A�܂悤���@�Ƃ���
�Ɠ��̖������ł���Ă݂�ƁA���̎��u���V�̓������킩��܂����B �ꌩ����ƍd���Ė����ɂ��������ł������A�܂悤���@�Ƃ���
�Ɠ��̖������ł���Ă݂�ƁA���̎��u���V�̓������킩��܂����B
���Ԃ������Ă������A�������u��t���Ă�����ɂ͂����߂��Ǝv���܂��B
���̎��u���V���g�p���Ď����a�����P���ꂽ�Ƃ������Ƃł����A
�m���ɍ��܂Ŏ��Ԃ̃v���[�N���܂��������Ƃ��ĂȂ��������ł�����A���ʂ�
���u���V���͎��Ԃ������₷���̂ŁA�����Ǝv���܂��B
������{�I�ɖѐ�̊p�x�͎����|�P�b�g�ɂ͌����ĂȂ��̂Ŏ����|�P�b�g�܂ŃP�A���ł����A����ȏ�̉��P�͓���Ǝv���܂��B
���̑��A�O���͌��₷���āA���₷���ł����A�P���̂Ƃ��ɐ㑤�͓��Ăɂ����Ɗ����܂����B
WF�ł͊F����Ƀt���X���g�p���Ē����Ă���̂ŁA�Ƃ��ɕK�v�Ȃ��ł����A
�g�p����Ƃ�����A
�������u��t���Ă�����̕⏕���u���V�Ƃ��Ă��A
���Ԃ��Ă��āA�t���X���Ǝ��̏�̕��������Ă��܂����ɂ����l�̕⏕���u���V�Ƃ��āA�i�t���X�͂������g�p���Ă��炢�܂��j
�܂悤������������ƃ}�X�^�[�ł�����Ɍ���Ǝv���܂��B
�y���c�z
�@
|
| �y���]�z |
WF��DH������e�X�g�����܂悤���@�B�R�O�N�ȏ�܂��ɂ͂�����APHB�n�u���V
�l���X�p�C�����@���l���邫������������Ă��ꂽ�A�u���b�e�B���O�@�̌���ŁH
�������A�ѐ悪�d���ƁA���̂����͗אږʂ����������Ă���̂ŁA���ʂ₦�G�i�������̕\�ʂ������A���p���̂��茸��A�m�o�ߕq�AWSD�Ɍq����B
�אږʓ�����͖����Ă��A��͂�n�u���V�Ȃ̂ŁA�אږʂ̉������̂S�����̕����ɂ͓͂��Ȃ��A���������ŁA���ԃu���V���g��ꂽ��A�אڍ��ʂ͂P�O�N��ɂ́A���茸���
�v���[�N�͂Ȃ��Ă��A�אڎ��ԕ��͊J���āA���Ԃ��炯�̎��������ɂȂ�܂��B
���N�Ȏ����̕������̎������@�ł͂���܂���B�����a���i��ł��܂��A����ɂ��̂܂悤���@�ł́A�B�ꎕ���a�����܂��B�Ȃ����āA�͂��Ȃ��אڍ��ʃ|�P�b�g����
�����@������E�E�E�E�E�אڐڐG�_���͂������Ȃ��H�H�H
�@ |
top�֖߂� |
| 2.�z���C�g�t�@�~���[�̉q���m���� |
���Ȑf�Î��̕s���E���|�Ǝ��ȐS�g��w
DH�|�� |
���Ȑf�Î��̕s���E���|�Ǝ��ȐS�g��w
����ł����Ȃ��炸���Ȏ��Âɑ��ĕs���E���|�������A���ɂ͋��|�̂��܂�A��ŕ�����
������A�����J���Ȃ��悤�ȍs���ȂǂŁA�\���Ȏ��Ȏ��Â����Ȃ��ł��鎕�Ȏ��Ë�
�ǂ̐l������B
���ȋ��|�ǂ⎡�Âɑ��A���x�̕s���E���|������Ă���A�����ɂ��Ēm����L����
���邱�Ƃ͕K�v�s���ł���B
�Ώ��@�Ƃ��ẮA
�@
���ȐS�g��w�Ǝ��ȐS���w�̗v�f���K�v�Ƃ����
| �S�g��w�E�E�E |
�g�̖ʂ����łȂ��A�S���ʁA�Љ�ʁA���ݖʂ����܂߂đ����I�A�����I�ɂ݂Ă������Ƃ����w�ł���B
���Â��銳�҂͐��g�̐l�Ԃł���A������w���f���i�A���˔\�A�O�Ȏ�p�Ȃǂ�p���Ď��Áj�ɒ�߂��S�l�I���f���i�g�́E�S���E�Љ�I����Ȃǂ��画�f�j�Ƃ��Ă݂Ă����B
�@
|
| �S���w�E�E�E�E |
�����̂̐S�̓�����s������������w��ł���B
|
���Ȏ��Â̍ۂɂƂĂ��ɂ��v����������A�C���������Ȃ�����Ɗ�@�I�Ȃ��̂Ɋ�����ƁA��
�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁA�\����s��������悤�ɂȂ�B����̎��Â̊ԂɁA�H�~���Ȃ�
�Ȃ�����A�s���⒍�ˊ�����������ŋ��|�����������Ƃ�����B
��ʈ�Ȉ�Âł̕s���ȑ̌����֗^���邱�Ƃ�����B
�Ƒ�����͂̎��Ȏ��Âւ̋��ۓI�ȑԓx���������������ŁA�s����������Ƃ�����B
���҂����Ԃ�s���̌����̕s���x�́A����قNj����Ȃ��Ă��p��ɖ��������A�P��
�̑̌��ŕs�����̌�������Ȃ��̂ł�������ƁA�N�ł������ȋ��|�ǂǂ���\����
����B
���A���x�̕s����������₷����:
�����퐶���Ŏ��Ȏ��ÈȊO�ɂ����Ȃ�s���i�Z�����s���j���݂Ƃ߂����
���_�o�njX���̋�����
���_�o�ǂ�S�g�ǂ̊����̂���҂⌻�ݜ늳���̎�
���O���I���i�҂ɑ��ē����I���i��
�����Ƃ����A����A���N�A��p�ȂLj�w���ÖʂɊւ��ċɓx�̒��ӂ�����₷���҂�S�C�I�X���̋�����
���Ȏ��Î��̕s���E���|�̌y�������@
�s���⋰�|�͖����I�ɒ��������Ă��܂��Ə����͍���ɂȂ�B
�ُ�s���͑f���ł͂Ȃ���V�I�Ɋw�K���ꂽ���̂ƍl������B���������āA�w�K�̌�����
����āA�K�Ɋw�K�������̂����ÂƂȂ�B
�ӎ��△�ӎ��ɓ���������̂łȂ��A�w�K�ɂ���đԓx�̕ϗe�⎡�Â̌��͂���ʂ��グ�悤�Ƃ�����@�ł���B�i�s���Ö@�j
�s���Ö@�̎菇
| �P�����ʐځE�E�E |
���݂̏Ǐǂ̂悤�Ɋw�K����A�������Ă������͂��s���B
���s���i�Ǐ�j���������邽�߂ɉ�������ڕW��ݒ肷��B
�ڕW�ɑ��Ď��Ìv������āA�v��Ɋ�Â��Ď��Î�i���l���A���s�Ɉڂ��B
�@
|
| �Q�s���K�w�\�̍쐬�E�E�E |
�s���������N�����h����ʂ��������̂���ア���̂ւƔz���\���쐬����B
�@
|
| �R�����b�N�X���i�̎w���E�E�E |
�s�������̕\���Ƃ��ċ؋ْ����g�̕\���Ƃ��Č����B
���ȈÎ����烊���b�N�X�̏�Ԃ�����Ă��������P���@���A�g�̂̒o�ɂƋْ��̈Ⴂ��̓����Ȃ���w��ł��������b�N�X�@�B
�ؒo�ɖ@�̕������ʓI�ł��낤�Ƃ����Ă���B
�ؒo�ɖ@
�����P���@
�@ |
| �S�E����̎葱���E�E�E |
�@���҂Ƀ����b�N�X�����獇�}�i����j������B
�A�s�����N�̍ł��Ⴂ�h����ʂ�z��������B
�B���̏�ʂɂ��A�s����ْ����������ꍇ�͍��}�����A�r�t�c��q�˂�B
�C�ēx�����N�Z�[�V�������w�����A�Y����ʂɂ�苓�肳��Ȃ��Ȃ�����A�ْ����������������ƂɂȂ�A���̍��ڂɈڂ�B
�D�N�ł������Â̍ەs���������Ă��邪�A�r�t�c���Q�O�_�ȉ��̕s���͒N�ł��������Ă��鐳���̂��̂ł���B
�r�t�c���Q�O�_�ʂɉ���������A�C���[�W�ł̒E����ł͂Ȃ��A���ۂ̏��u���s���Ă����Ƃ��������E����Ɉڂ��Ă����B
�E����ł��o�ɌP���̗��K�ƂƂ��ɒE������s�킹��B
�F�咣�P���̕��p������B���Ȑf�ẤA����Ɠ������Ǝv���A�����̊����\�����ɂ����҂�����B
���Âɋ^�₪����Ύ��₵�A�����ł��Ȃ��ꍇ�͒f���Ă��悢�Ƃ������Ƃ�������B |
�r�t�c�E�E�E���o�I��Q�P��
�r�t�c�̒l�͊��Ҏ��g�̐\���l�ł���A�P�O�O�����ł������s���������N�����h����ʂƂ������Ƃł���B
���̂悤�ɂ��āA�|�����Ă������Â�����悤�ɂ��Ă����B
�q�f�����ȂǁA�s���̂Ȃ��ʼnߏ�ɔ������Ă��܂�����A�����t�ŕs�����������A�����M�[�������Ǝv������ƁA���낢��ȏ�ʂ͂悭���܂��B���҂̐��i��ώ@�͂������ł���ȂƉ��߂Ă��������B
�ꌩ���邭�A�ǂ��b�����҂���ł��A���w�S���͓����ł��B���ȗ}���ɂ���āA�\�ʂɌ���Ȃ��A�R���g���[������Č����Ȃ������ł�����A�����A�ǂ�Ȋ��҂���ł��A�킯�u�Ă̂Ȃ��A�₳�����Ɩ����̑Ή��ŁA���҂���̃R�R���ɓ͂��A�P�A�����Ă��������B���҂���̂����Ă���y�[�X��ǂނł��B |
top�֖߂� |
| ���Ȑf�Î��̕s���E���|�Ǝ��ȐS�g��w
DH���c |
�N�ł����Ȃ��炸���Ȏ��Âɑ��s���E���|�������Ă���B
���ɂ͂��̒��x�����܂�ɂ����x�Ȃ��߁A��Ŏ��Ê����̂�����A
�����J���Ȃ��Ƃ����悤�ȓ����s�������݂���A�ʂĂɂ͎��Ȏ��Â��ɎȂ��Ƃ�������s����悵����ƁA�\���Ȏ��Ȏ��Â����Ȃ��ł��鎕�ȋ��|�ǂƂ����A�s�K���s���������Ă��銳�ҌQ���F�߂���B
���ȋ��|�ǂɑ���Ώ��̎d�������܂����B
| �P�E���@�� |
�@ |
| �Q�E�����ʐ� |
���݂̎��ȋ��|�ǂ̏Ǐ����Ȃ���Ŋw�K����A�������ꂽ��
���w�K���_�̗��ꂩ�番�͂�����B�ꍇ�ɂ���Ă͑��Ȃֈ˗�����
�@
|
| �R�E���ÖڕW�̌��� |
���s���i�Ǐ�j���������邽�߂ɉ������ׂ��ڕW��ݒ肷��B
�@
|
| �S�E���Ìv�� |
���ÖڕW�Ɋ�Â��ċ�̓I�Ȏ��Î�i���l����
�@
|
| �T�E���Â̎��s |
|
WF�ł͏��f����CC������̂ŁA�����Ȃ莡�Âł͂Ȃ��A���̎��ɘb����̂ň��S�������������Ǝv���܂��B
�ْ����āA���Ò��͂�����ƁA�ɂ��ƌ������Ƃ������Ȃ�������A���Ö@��ς��Ăق������Ƃ������Ȃ��l������悤�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ł�������悤�ȃ����b�N�X������Ԃ��������A������悤�ɗ��K���Ă����̂������悤�ł��B |
top�֖߂� |
| �����a�ɂ������̖͂��
DH�|�� |
���o�Ƃ�������
���R�ړ��̎傽�錴���͒��o�Ƃ������팻�ہB
���o�͕͂��o�Ƃ̂�����肪��肴������Ă���B
���̕��o�́A�킸���Ȃ���₦�ԂȂ������Ă���A���̌����ɂ��A���������Ȃ��Ȃ���o���Ă���B
�������A�����ԑ����Ȃ��Ă����o���݂��Ȃ��Ǘ�����т��т���B
�T���ł̎����ɂ��ƁA��{�P���ł́A����������U�T�Ԃ����o���A�Q�N�o�߂������_�łR�O�`�T�O���̒��o����ɒ��o����X�����݂�ꂽ�B
����A���{�P���ł́A������R�������߂���ƒ��o�̓x�����͎キ�Ȃ�A��{�ɔ�ׂ�Ə��Ȃ��B
�܂�A��{�P���͉��{�P���������o�X�����������Ƃ��킩��B
�����Ƃ��ẮA��{�̎����d�͂̍�p�����ɁA���{�̎��́A�d�͂ɋt����Ē��o�ł��낤�ƍl������B
���R���o�̃��J�j�Y���́A�܂��͂�����Ɖ𖾂���Ă��ȁB
��{�I�ɂ́A���������̑��s�A���ǂɂ����ۂ̔j��A�Z�����g���`���ƊW���Ă��邱�ƁB�������������A�ݎ��A�j�S���A��ȂǂɐڐG�����A�O�͂��Ȃ��ꍇ�A���������ۂ̑��s���킸���Ɏ������Ɉړ�����B�i�I���o�^���j
����ɑ��A�����g�D�ɉ��ǂ�����A����������ۂ⒆�u���f���ۂ��j���ƒ��o�̒��x�͒����ɂȂ�B
����ɁA�߉��S�I�A�j��I�Ɏ��ʂɑ�����ې��t���̔j�قȂ�Ǝ��̈ړ��������ς��B
���ۓ��m�̈������肠���ɂ��j���Ȃ������Ɉړ�����B
���̑S���ɂ킽�蓯���x�̔j����A�������������Ɉړ��������ƐڐG�������_�Œ�~����B
���o�̃��J�j�Y���Ƃ��āA���������ۂ⎕�����ۂ̈������荇�����d�����Ă��邪�ʂ̈��q������̂ł͂Ƃ̂��ƁB
�������ɔ����ċN����[�������ُ̈�ȓˏo���邱�Ƃ͒m���Ă���A���ǂɍۂ��āA
*�v���X�^�O�����W���Ȃǂ̐��̕��������Y����A�Ǐ��̌��Ǔ��ߐ��i����������g�D�t�������߂邱�Ƃ��l������B
�܂�A���������������ɂȂ���o�͂ɒ��荇���������ۂ�j��Ɠ����ɁA���ǂ��������ɍL�܂邱�Ƃɂ��A��������ʂƂ��ċN����g�D�t���̍��܂肪���o�͂��������ƍl������B
| ���v���X�^�O�����W���E�E�E |
�R�̃O���[�v�ɕ�����A���G�ȕω������Đ��\��ނ̃v���X�^�O�����W���������B
���̍�p�́A���ǁE�ɂ݁E���̒����E�����E�S�@�\�E�ݒ��@�\�Ə����y�f�̕��咲���E���ؗU���Ȃǂ̐��B�@�\�̐���E�t�@�\�Ɨ������߁E���t�Ìłƌ����^�W�E�A�����M�[�����E�_�o�`�B�E�e��z�������̐��Y�ȂǂɊW���Ă���B |
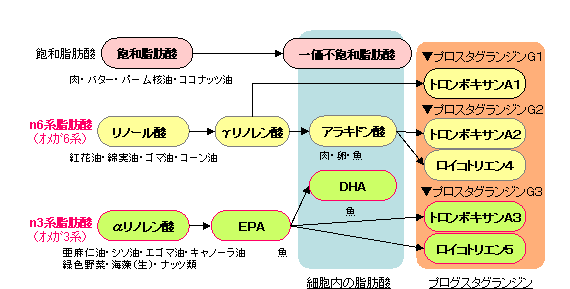
���R���o�̗Տ��ώ@����
�ΏہE�E�E�����a���x�`�d�x�B
�v���[�u����������o����r�^�B
�������̊������̍����Ǝv���鎕��Q�O�{�B
�C������P�����A�����̃X�y�[�X������A���R���o�����ώ@�B
�����I���h�x���Ȃ��ꍇ�́A���o�����҂��邱�Ƃ�����B
���o�͂̉�����ɂ����ɑ��₩�ɋN����B�ʏ�Q�T�Ԓ��x�ő傫�Ȓ��o�^���͏I�����A���Â��i�ނɂ�A�����̐����p�������Ă��邽�߁A���R���o�͌������Ă���B
���������āA�Ȃ�ׂ����������ɒ��o�������Ă݂�ׂ��ł���B
���[�g�v���[�j���O���s�����ǂ����ނ�����ɒ��o�͂����҂���͓̂���Ǝv����B
���������������ɂȂ莕�����ɉ��ǂ��L���邱�Ƃɂ����o���N����ƍl����ƁA���ǂ̃R���g���[���Ƃ��������a���Â̌����͕ς��Ȃ��B
�d�x�����a�����Ő����I���h���������ꍇ�A�ʏ�̉��ǂ̃R���g���[�������ł͓��h�͂����܂�ɂ����A�������ۑ����̑I���ɔ����邱�Ƃ��玩�R���o�̓K���ǂƂȂ�B
��_�Ɏ��������퍇������̍s�����������Ɉړ������邱�ƂŁA�g�D�t���̍��܂���J�����A�������ɍL���������ǂ̌y�ł�}��B
���̎��_�ŕۑ��̉\���̂��鎕��͑����̏ꍇ�A�����I���h�̉��P�������A�Ȍ�̎������Âɂ��ǍD�Ȕ������������Ƃ������B
�������A���h�̉��P���v�킵���Ȃ��ꍇ�́A�����Ƃ����f�f�������Ă��ԈႦ�ł͂Ȃ��Ƃ����Ă���B
�b�ԌŒ�����Ă����ꍇ�́A���̂悤�Ȏ��Â����҂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv�����B |
top�֖߂� |
| �����a�ɂ������̖͂��
DH�u�c |
�@
���h���̎b�ԌŒ�F�A�����邱�Ƃɂ��������O����h��
�����g�D�����Âɕۂ��߂ɍs���B
�����������悤�Ȋ����ɂȂ�̂������̑����ɂ����o���T�^�I
�ł���B
���R���o�F�͂�����Ɖ𖾂���ĂȂ����������@�ۂ̑��s�A
���ǂɂ��@�ۂ̔j��A�Z�����g���`���ƊW���Ă���Ƃ̂��ƁB
�����a���d�x�ɐi�s���Ă��鎕��A���ɐ����I���h�����Ă��鎕�傪
���o���₷���B
���������̃��[�g�v���[�j���O���s�����ǂ����ނ�����ƒ��o�͎~�܂�B
�T�����g���������ł́A��{�P���͑r����6�T�Ԃ����o�̌X�����݂��A
2�N�o�߂������_�ł͂R�O���`�T�O�����o���A����ɒ��o����X��������ꂽ�B
���{�́A3�������߂���ƒ��o�̓x�����͎キ�Ȃ�A
���̕ω��ʂ���{�Ɣ�ׂĂ͂邩�ɏ������B
�A�u�Z�X�̌`����������ꍇ���؊J���s���A�����܂����f�u���C�g�����g���s���B2�`4�T�Ԃ��炢����������I���h�͗��������Ă���B
�f�u���C�g�����g����␅���������邱�Ƃ������B
���̌���������O����h�����߂ɂ��Œ����K�v�B
�A�u�Z�X�����Â�������t���b�v���s�����Ƃɂ�莡���ɑ��锽����
�ǍD�ɂȂ�B
�Œ�F���s���ꍇ�A
�`�Ԃɂ���Ă͐��|���������v���[�N���t���₷���Ȃ�̂�
���C���e�i���X�̂��₷���A�����|����̂Ȃ��X���[�X�`�Ԃ���邱�Ƃ�
�t���X�P�A�⎕�ԃP�A���w������
�v�e�ł͍R���܂ɂ�鉻�w�I�|�P�b�g�P�A���s���Ă��܂��B
|
top�֖߂� |
| �����a�ɂ������̖͂��
DH���c
|
�@
�����g�D���j��Ă��ĕۑ�������Ǝv���鎕���A�퍇���o�C�g��Ⴍ���āA���R���o���˂炢�A�����g�D�̉𑣂����Ƃɂ̓r�b�N�����܂����B
�b�ԌŒ�����ẮA�����Ȃ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̊ԃA�u�Z�X���ł��Ĕ�����������A��Ԃ�������A�Ǝ��Ó�������Ԃ�������܂����A��������P�I���łȂ��̂ŁA�s���Ă݂鉿�l�͂���Ǝv���܂��B
|
top�֖߂� |
| �C�r�L�������ċz��Q
DH�|�� |
�@
�C�r�L�������ċz��Q�ɉ���I�ȃX���[�v�X�v�����g����
�C�r�L�ǂ␇�������ċz�nj�Q�Ƃ����������ċz��Q�֘A�����́A������Ȃ̗̈�Őf�f�E���Â��ꎕ�Ȃ̕���Ƃ͖����ł������B
�C�r�L�̎��Âł́A�������Ƃ��Č��W������W�������`�p�Ƃ����̂ǂ̎�p��A�A�ɂ��Ȃ������C�����m�ۂ�����@�i�C�ǐ؊J�p�j�ȂǁA�C�r�L��ċz�͉��P����������Ȃ����A���͏o�Ȃ��Ȃ�A�J�������犴���̋��������A�x�Ⴊ���������˂Ȃ��ƂȂ�A�������ȑ�w��w���Ƃ̌����J�������̂����o������B
���̑�����X���[�v�X�v�����g�Ɩ��t�����B
�C�r�L�△�ċz�������ċz��Q
�얞�ɂ������A�{�̎��s���ŋN�����X�y�[�X�̕s���������ŏ�C���i�@�o�E�����E�A���j�̋���ѕǂ��N���A��������̒����N�j���ɑ����݂���B
��ꂽ���ɃC�r�L�������̂͂���قǐS�z�͂Ȃ��B�K�������A���ӂ̂悤�ɃC�r�L�������Ă����Ԃ��K�����C�r�L�ǁihabitual snoring�F�g�r�j�Ƃ����B
�p�x�������Ȃ�ƁA
��C����R�nj�Q�iUpper airway resistance syndrome�F�t�`�q�r�j�ƂȂ�A����ɂ́A
���������ċz�nj�Q�iSleep apnea syndrome�F�r�`�r�j�ւƈ�������B
���{�l�ŏK�����C�r�L�nj�Q�́A�Q�O�O�O���l�ȏ�A�łP�O���ɂ�����Q�O�O���l�����������ċz�nj�Q�ƍl�����Ă���B
�K���I�ɃC�r�L�������l�́A
���������ċz�nj�Q�̗\���R�ł���B
���ċz�w���iApnea index�F�`�h�j�E�E�E�����P���Ԃ�����P�O�b�ȏ�̌ċz��~�i���ċz�j��
�`�h�̒l������������قǂr�`�r�͏d�ǂł���B
�P�X�W�W�N�ɁA�X�N�Ԃɂ킽��o�ߊώ@�����Ƃ���A�`�h�w�����Q�O�ȏ�̌Q�ꂪ���炩�ɐ����\�オ�s�ǂł��鎖���\���Ă���B
����ȍ~�`�h���Q�O�ł��邩�ǂ������@���ÊJ�n�̈�ɂȂ�B
�\������E����z�n�����ǂ̊ϓ_����
�����_�f�O�a�x�i�r���n2�j�E�E�E���N�Ȑl�Ȃ�A�N���Ă��鎞�͏��97���ȏ�ۂ���Ă���B
�A�Q���ɏ�C���̋����ǂ��N������Ȍċz���ł��Ȃ��ƁBSaO2���ቺ����B
SaO2�̍Œ�l���V�O���A��������SaO2���X�O���̎��ԁi��_�f���I���ԁj���������Ԃ̂T�`�P�O���ȏ゠��Ǝ��Â̑ΏۂƂ����B
�����X���Ȃǎ��o�Ǐ��퐶���ɑ傫�Ȏx����������Ă���ꍇ���������̂悤�ȂƂ��͎w���W�Ȃ����Â��K�v�Ƃ����B
�r�`�r�̌y�ǂ�t�`�q�r�C�g�r�̏ꍇ�́A���N�ی��̓K�p���珜�O����Ă���̂ŁA�X���[�v�X�v�����g���Ö@���ȒP�Ō��ʓI���B
���������ċz�nj�Q�F�r�`�r
�r�`�r�ɂ͂R��ނɕ�������B
| �����^�iCentral SAS�FCSAS�j�E�E�E |
�ċz�^�����̂��̂���~���Ė��ċz�ƂȂ�B�𐑂ɂ���ċz��������ċz�ɑ��Ă̎h������~���Ă��܂��A�ċz�^�����S���Ȃ���ԁA�܂�A�@��������łȂ����s�≡�u���ɂ��ċz���Ă���`�Ղ��Ȃ����ƁB�����Ƃ��ẮA�]�����ɉ��炩�ُ̈킪�l������B���ȓI�Ö@�ł͑Ή��ł��Ȃ��B
�@
|
| �nj^�iObstructive SAS�FOSAS�j�E�E�E |
��C���̈ꕔ���ǂ��邱�ƂŖ��ċz�ƂȂ�B�����ǂ̌ċz�^�����s���Ă�����̂́A�@�o����o�ɂ�����C������~���Ă����ԂŁA�������ɋC���������I�ɕǂ���Ĉ����N���邱�ƁB
�@
|
| ���^�E�E�E |
�����̌^�������Ă���B |
�����̂R�̕a�^�̒��ŕnj^�����|�I�ɑ����A�r�`�r�̂X�O���`�X�T�����߂Ă���B
�قƂ�ǂ̂r�`�r�ɑ��ăX���[�v�X�v�����g�Ö@�͓K�p�ł���B
��C������̉e�����q
| �`�ԓI�ُ�E�E�E |
���{�ǁA����s���A�A�f�m�C�h�A�G�����A�����A�얞�ɔ�����C����g�D�ւ̎��b�����A�߂ُ̈�i���E�}�`�ɂ��j���{���̌���ψʂ�����B
�@
|
| �@�\�I�ُ�E�E�E |
��C���i�I�g�K�C�㍜�A�I�g�K�C��A���W�����j�̊����x�̒ቺ������B |
�ł�����������̂́A�얞�ƂƂ��ɐオ��剻���邱�ƁB
�����Ă��Ă��A�オ��債�Ă��邱�Ƃŏ�Q���ł�B
�A�Q���ɋ����̎p�����Ƃ�ƁA�d�͂Ő㍪�����ŃC�r�L���邱�Ƃ������B
���̓x�����������Ȃ�ƈꎞ�I�ɏ�C�������S�ɕǂ��Ă��܂����ċz�Ɋׂ�B
�����ċz��Q�̕��Q
�g�r�A�t�`�q�r�A�n�r�`�r�̂�������傫�ȃC�r�L���B�̂ɑ傫�ȕ��S�������邾���łȂ��A�Љ���ɂ����Q���y�ڂ��Ă���B
�����ċz��Q���������������A�������ǁA���A�a�Ƃ����������K���a�������N�����A����ɐS�؍[�ǂ�]�����Ȃǂɂ�薽�𗎂Ƃ����Ƃ�����B�W���͂�v�l�\�́A���f�͂�ቺ�����Ă��܂����Ƃ�����B�i�����ɓˑR�̖��C�Ȃǁj
�����ċz��Q�̎��Ö@
�r�`�r�̎��Ö@�͓��ȓI�A�O�ȓI�A���ȓI�̕������邪�A�傾�������Ö@�����ɂ���B
*�̏d�̌��ʁE�E�E�r�`�r�̓����͔얞�̊��҂������B
���Ԃ��v���邱�Ƃ�{�l���g�̓w�͂Ɉˑ�����B
���ʂ��Ă����P���Ȃ����Ƃ����邽�߁A���̎��Ö@�ƕ��p������Ȃ����Ƃ������B
*��b�����̎��ÂƗU���̏����E�E�E�@�̎��Â�֎��A���������ɍ܂̕��p���~�Ȃǂ̌��������Ö@�Ɨ\�h���d�v�ɂȂ�B
*�����̈ʂ̎w���E�E�E�����ł́A�㍪�������₷���A�C�������������Ė��ċz���N����₷���B�������ł̏A�Q���w������B
*���ċz�̗}���E�E�E�{���A�@�ċz������ł���A���ċz�ɂȂ�ƋC���������Ȃ�A�C�r�L�△�ċz�ɂȂ�₷���B���ċz��h�~���邽�߁A�A�Q���Ɍ��Ƀe�[�s���O���A�@�ċz�ɓw�߂�悤�Ɏw������B
*�O�ȓI���ÁE�E�E�������G�����A�A�f�m�C�h�A�@�|���[�v�Ȃǂ͂����肵�Ă���A�E�o��؏����s���B�C���ǂ̌������������ɂ���ꍇ�͎��@�ȓI��p�@���s����B�ꎞ�悭�Ȃ��Ă�2�`3�N�Ō��ɖ߂�l�����Ȃ��Ȃ��B���Ì��ʂ̂Ȃ��ꍇ�́A�C�ǐ؊J���ŏI��i�ɂȂ�B�����o�Ȃ��A�I�����̐S�z������B
*�o�@�I�����z���ċz�푕���iP-PAP)�E�E�E�@�ɃS���}�X�N�����A��舳�͂̋�C�𑗂肱��ŏ�C���̕ǂ�h�����u�ł���B���ċz�����������[�����𑝂₷���Ƃ��m�F����Ă���B
�`I���Q�O�ȏ�Œ��`�d�x�̂n�r�`�r�Ɛf�f�����Εی��K�p�ƂȂ�B
�������A��Ӓ������I�ɗz����������̂ŕs������A���J���J���Ɋ����A�����ԑς����Ȃ��l������B�����^�т�����ŁA���ӂ̑����̈ێ������ł���B�r�`�r��t�`�q�r�A�g�r�ɂ͕ی��K�p�O�Ȃ̂ŁA����ɂł������ł���킯�ł͂Ȃ��B
*�X���[�v�X�v�����g�Ö@�E�E�E��{��O���ɐ��~���ړ�������B��������Ɉړ�����̂ŁA�㍪�������h�~�����B
�K���ǁE�E�E�N�18�Έȏ㐸�_�I��Q���Ȃ��B�Q�����ǂ��B�����I�ȕ@�A�G�����A�A�f�m�C�h���ɂ���C���̉�U�w�I�ُ킪�Ȃ��B
���쎮�ċz�e�X�g���z���ł���B�i�@�̒ʂ肪�ǂ��Ȃ邱�Ƃ���
���ł���j�d�x�i��p�K���j�̏����{�ǂł͂Ȃ��{�߂̍\����@�\�Ɉُ킪�Ȃ����{�̑O�����������W�����ȏ゠��B���A�̂悢�c�������Q�O�{�ȏ゠��B�s�ǂ̃C���v�����g�E�s�Ǖ�ԕ����Ȃ��B
�X���[�v�X�v�����g�̓A�N�������W�����ł���B�ی��͓K�p�O�ł���B
�����ċz��Q�̐f�f�͈�Ȃ̗̈�Ȃ̂ňُ���`�F�b�N���Ă��炢�A����Ɍċz����ȁE���_�ȂȂǂ̐��������ȂǂƘA�g���āA���ȓI���Â�i�߂�̂��ǂ����Ǝv����B
|
top�֖߂� |